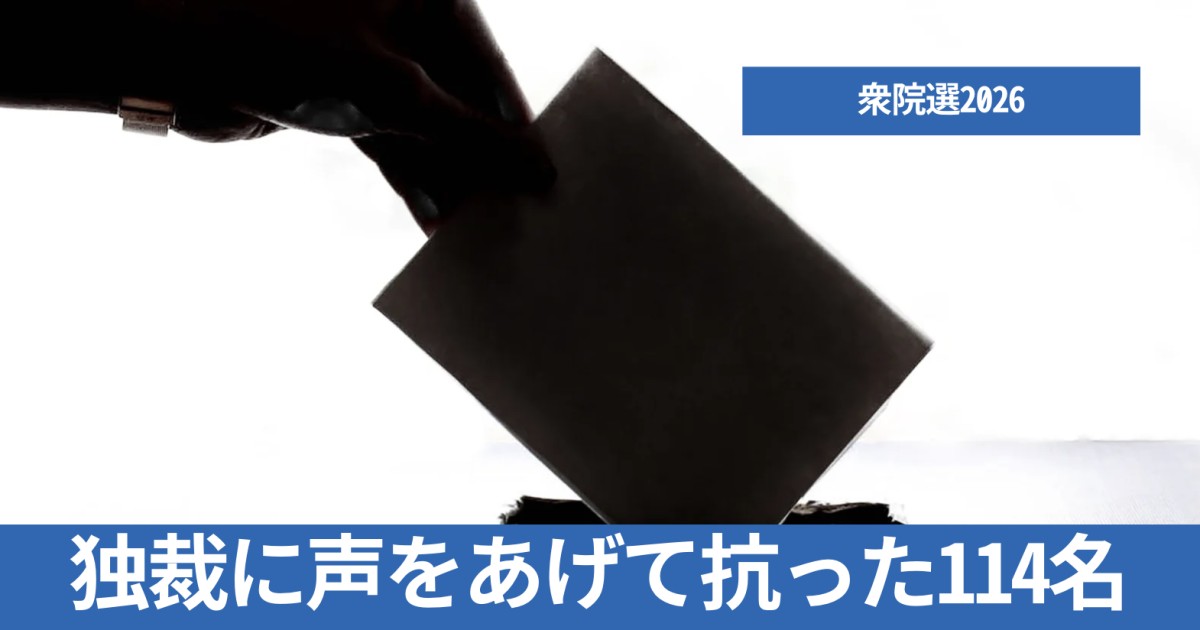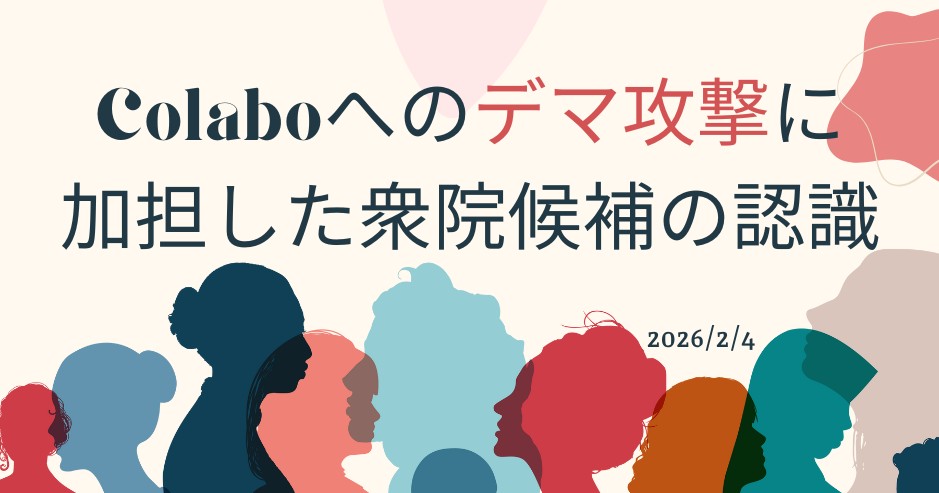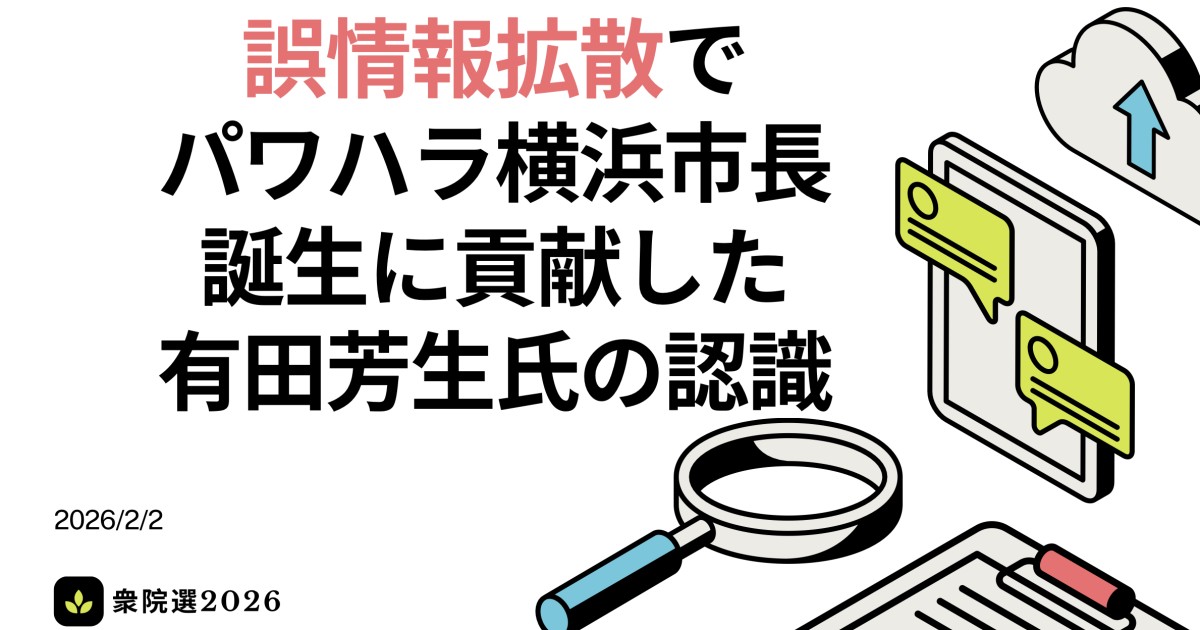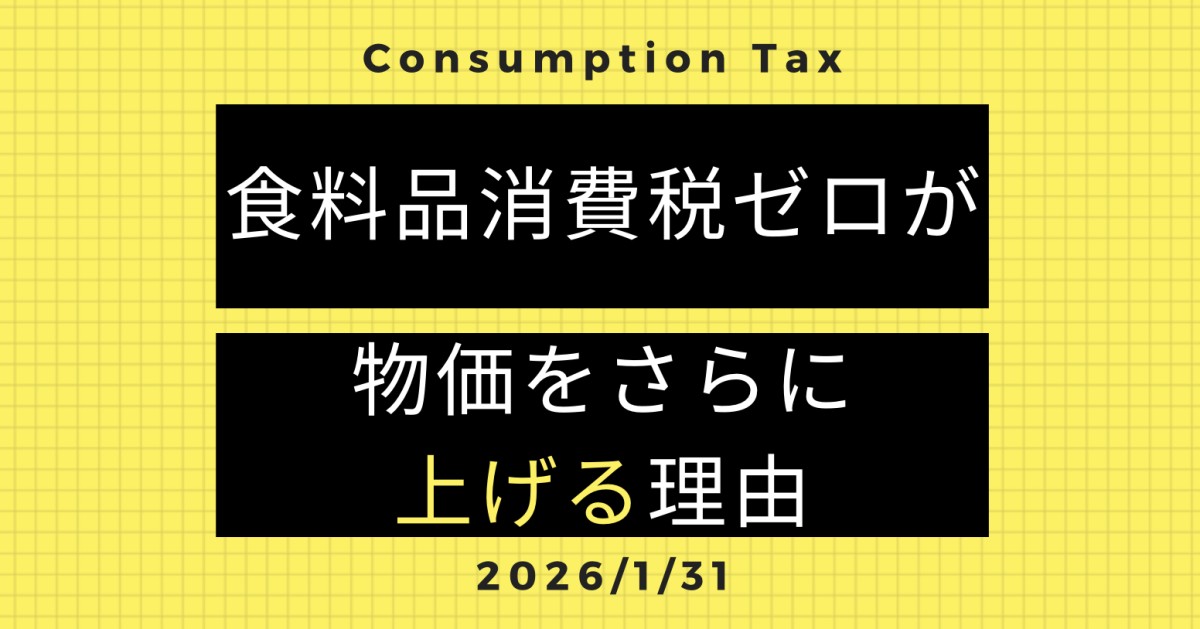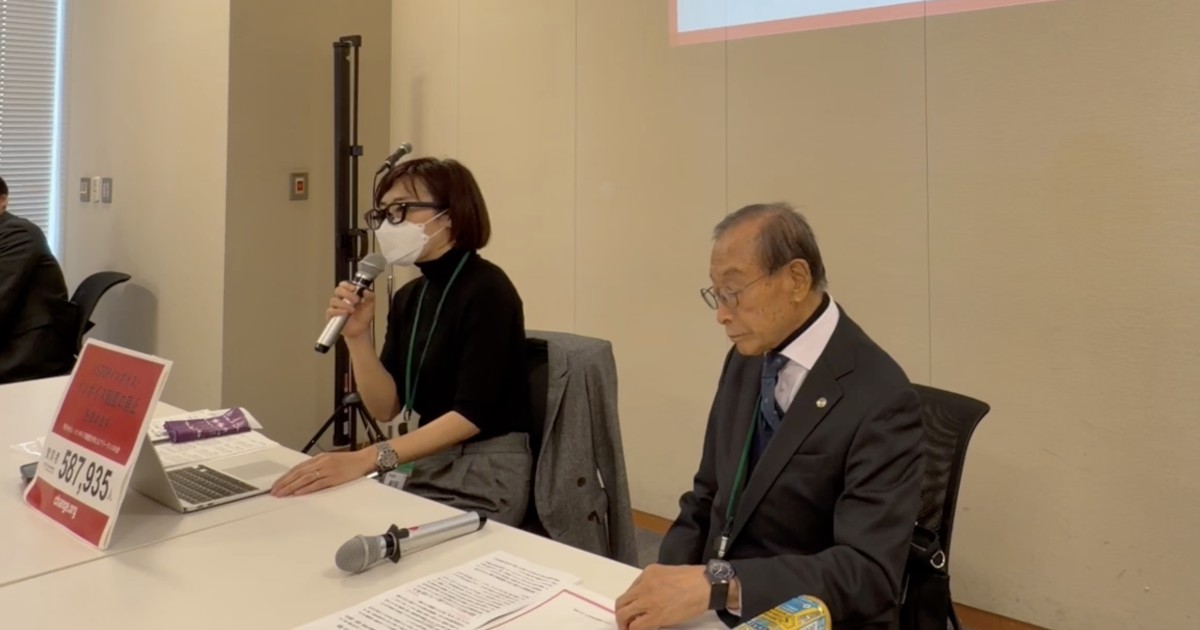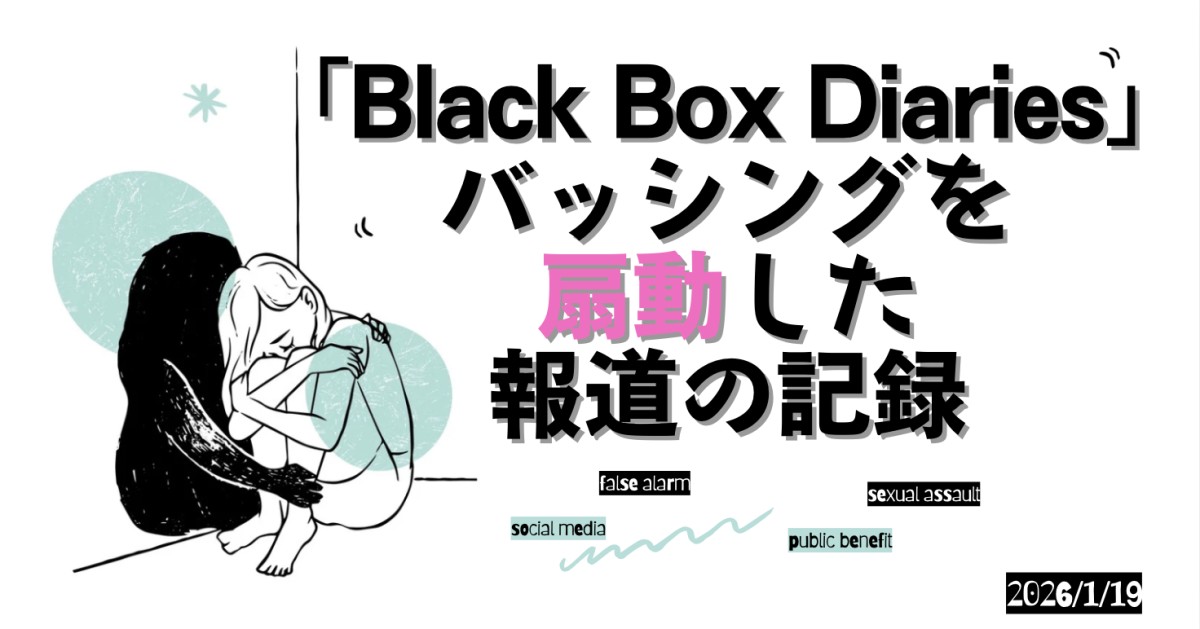「私たち消費者は消費税を支払っていない」 判決と法律に基づいて益税の誤解を解く
*今回のニュースレターは公共性が非常に高いと判断したため、無料読者にも本編を公開します
このニュースレターでは、様々なしがらみによって大手メディアが事実を報道しにくいテーマを中心に、しがらみのないフリーランスである犬飼淳が事実に基づいてお伝えしていきます。大手メディアの報道に疑問がある方は以下のボタンからニュースレターにご登録頂くと次回以降も見逃さずにチェックできます。
*ニュースレターの重点テーマ、特に反響が大きかった過去のコンテンツはリンク を参照ください
この記事を書いた理由
-
インボイスには妥当な導入根拠があると誤解している国民が一定数存在する
-
その原因として、「消費税は消費者が支払っている」「消費税は預かり金である」「だから、現状の免税事業者は本来納めるべき消費税を納めていない(=益税が存在する)」等の大きな誤解がある
この記事で理解できること
-
消費税を支払っているのは誰(消費者 or 事業者)なのか
-
消費税は預かり金なのか
-
益税は存在するのか
突然ですが、こちらのレシートをご覧ください。

これは私がカフェで350円のコーヒーを購入した際のレシートです。その350円の内訳には、消費税10%に相当する31円が含まれていると書かれています。
このレシートを受け取ったら誰もが「自分は350円のコーヒーを買った際に消費税31円も支払った」と考えるでしょう。
しかし、これは大変な誤解です。
さらに正確に言えば、消費者がそのように誤解するように仕向けられた壮大な嘘です。
そして、皮肉なことにそれが嘘であることは国が30年以上前の裁判で自ら認めています。
しかし、これらの誤解や嘘に基づいた「消費者が納めた消費税を免税事業者が横取りして納税しないのはズルい」という考え方を、インボイス導入の意義として多くの人が信じてしまっています。そこで今回のニュースレターでは、これらの益税をめぐる主張が完全な誤りであることを裁判の判例や法律の条文に則って解き明かしていきます。
*仕入税額控除などの基本的知識が無い場合は、インボイスの知識ゼロの方を対象に開催された勉強会リポートをあわせて参照ください
*公共性が非常に高いと判断したため、無料読者にも全文を公開します。メールアドレス登録のみで無料で全て読めるので、お気軽にご登録ください。
提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績