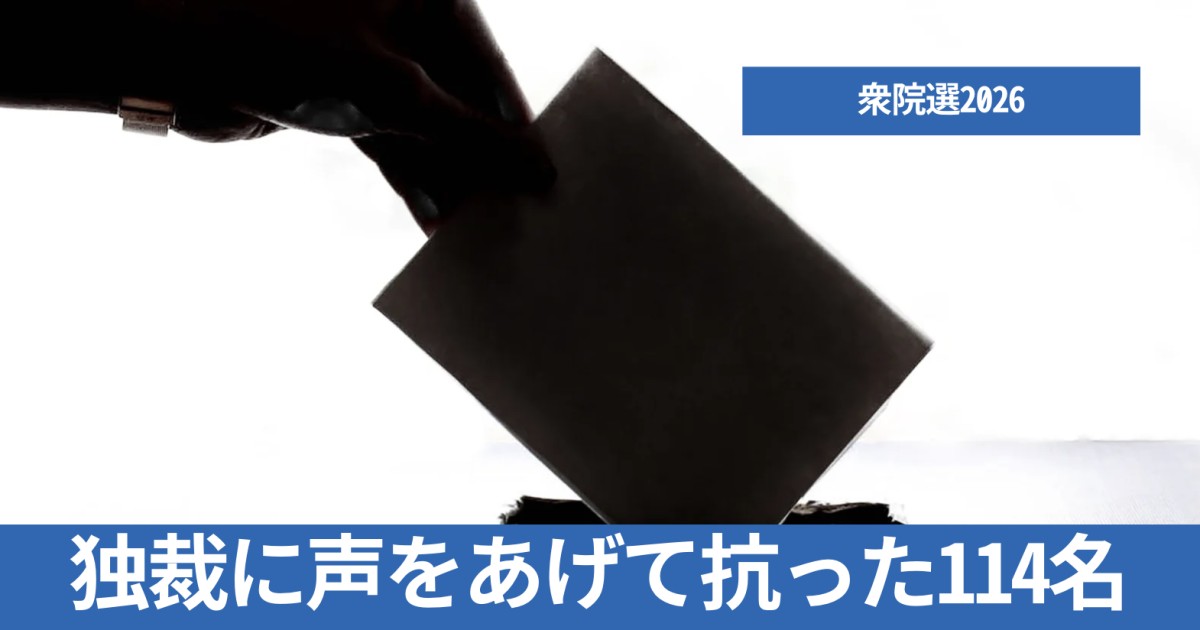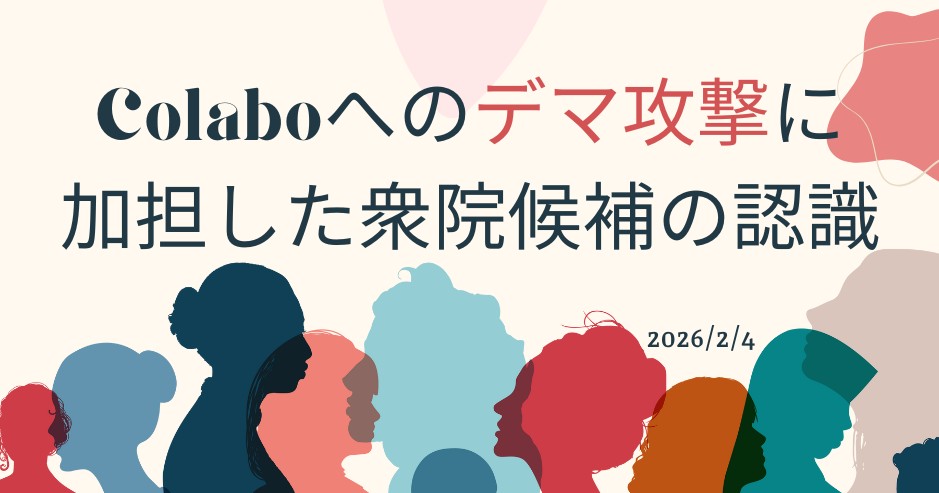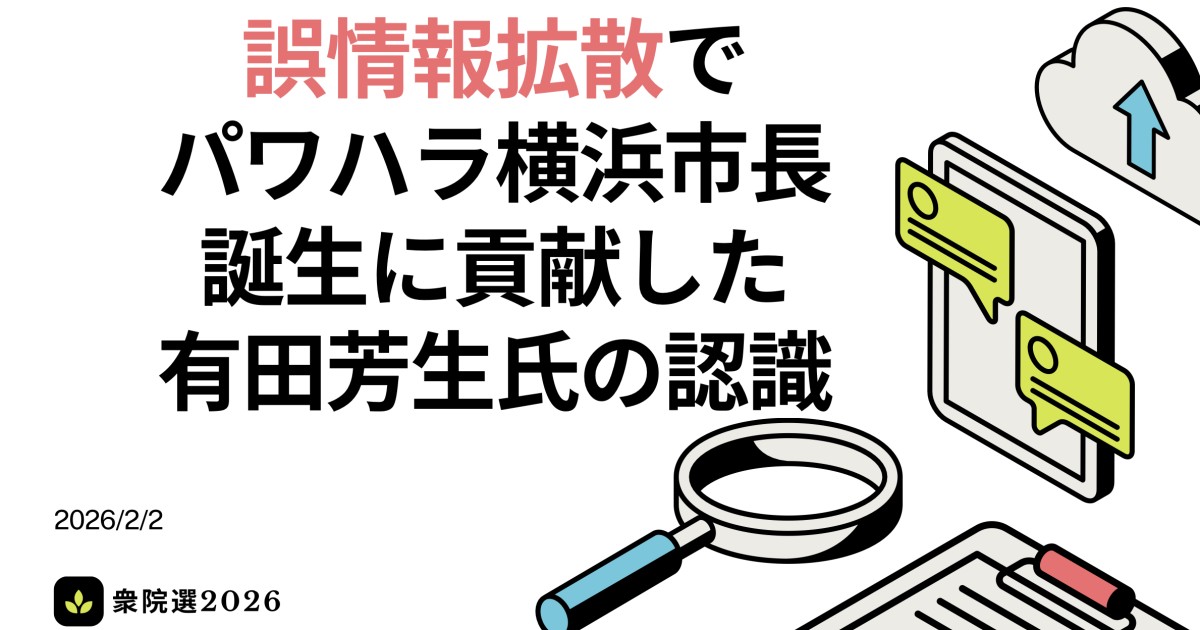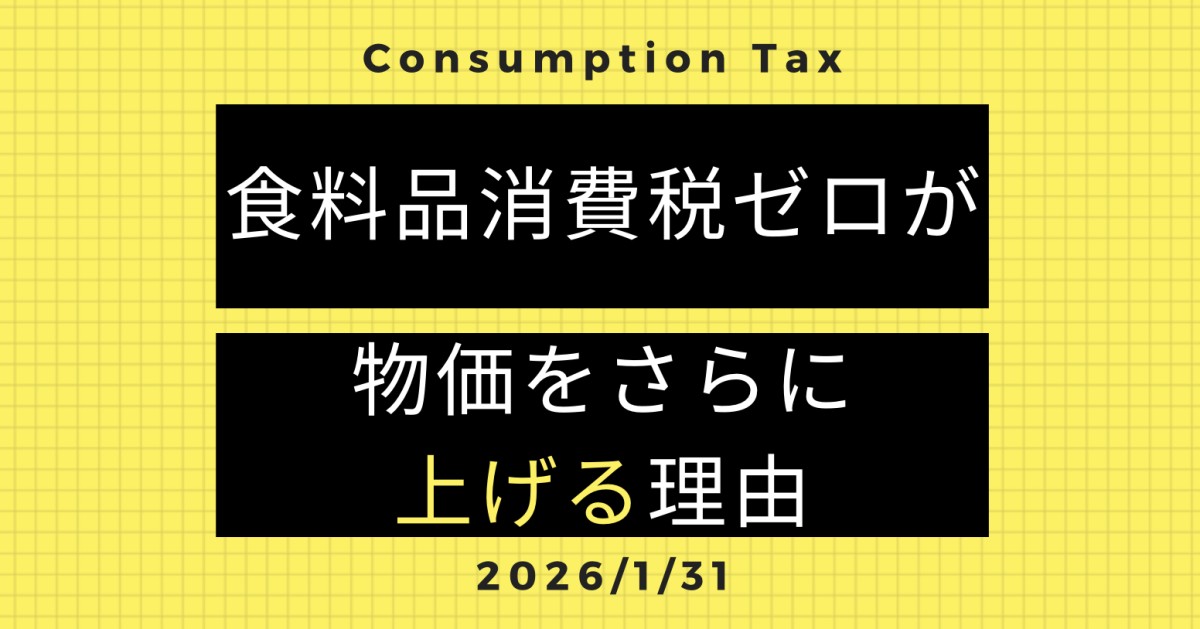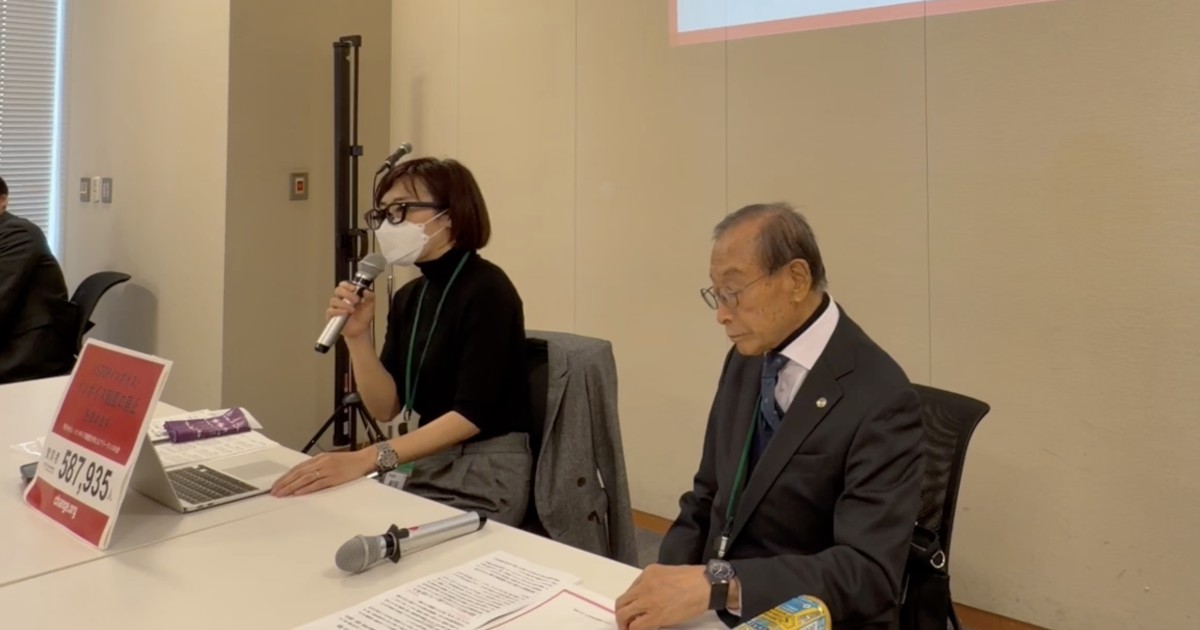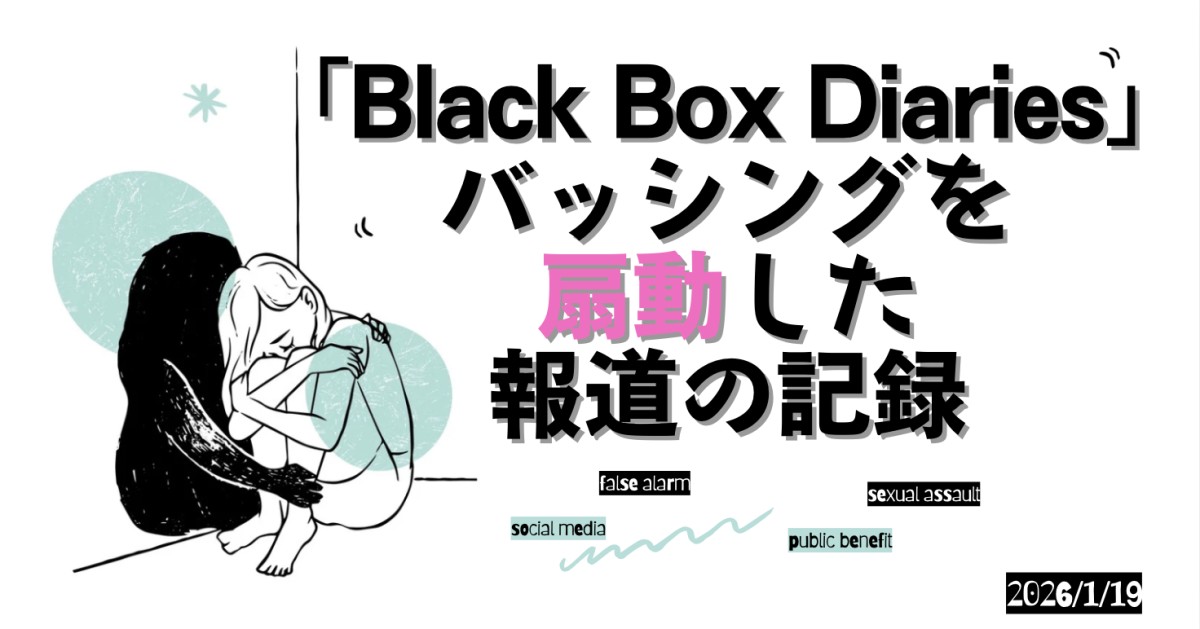役人の隠蔽(10)財務省が隠したかった「食料品の消費税ゼロ」への関与
このニュースレターはフリー記者の犬飼が「大手メディアが報じない読み応えのある検証記事」を月に4本以上(目安)配信します。皆さんの生活に影響する政策や報道の複雑な問題点を、視覚的に理解できるように工夫したスライドを中心に解説しています。
サポートメンバー登録によって運営されており、利害関係に縛られず取材・検証を日々行っており、総理大臣記者会見にも出席しております。サポートメンバー登録(月額600円〜、いつでも解約可)いただくと、以下の特典を得られます。
-
100本超の有料記事を過去配信も含めて全て購読できる
-
今後扱ってほしいテーマをスレッドで要望できる
サポートメンバーのおかげで私は継続しての運営が可能になり、より多くの報じられることのない事実を検証することができます。応援いただける方はぜひご登録をお願いいたします。
*ニュースレターの重点テーマ、特に反響が大きかった過去のコンテンツは「概要」を参照ください
この記事を書いた理由
-
行政文書の開示請求は、国民の「知る権利」を守る重要な手段である。行政機関(官公庁、自治体等)の情報公開の透明性が落ちた昨今、その重要性は一段と増している
-
しかし、あり得ない理由で開示請求を妨害する事例が後を絶たず、役人にとって不都合な情報は容易に隠蔽されている
この記事で理解できること
-
「食料品の消費税ゼロ」は財務省主導という疑念に基づく開示請求で入手した行政文書5件(計72枚)の概要
-
財務省が文書開示を避けるために選んだ巧妙な手口と、筆者が最終的に文書開示に成功するまでの3ヶ月に及ぶ攻防
4月下旬以降、複数の主要政党(立憲民主党、日本維新の会、社民党など)が減税・物価高改善という趣旨で「食料品の消費税ゼロ」(以降「本政策」と省略する場合あり)を公約として正式に掲げ始めました。しかし、日本の仕入税額控除の仕組みと消費税の実態に即して考えれば、得られる効果は以下の通り真逆であると筆者は考えています。
-
飲食店は食料品を仕入税額控除できず、ステルス増税となる。結果、外食産業の販売価格高騰・廃業が悪化する
-
他業種(小売・卸など)についても、もし「非課税」扱いであれば仕入税額控除できずステルス増税となる。結果、食に携わるあらゆる産業の販売価格高騰・廃業が悪化する。一方、「0%」扱いであれば特定業種のみ還付金を得るため業種間の不公平が生じる。もしくは、多数の零細事業者(八百屋、肉屋、魚屋など)への還付金にそもそも税務署が対応し切れない
さらに、将来的な可能性も含めると以下のような恐れも懸念されます。
-
税率が3段階に増えるため、「複数税率下での適切課税」を表向きの導入根拠とするインボイス(=事実上の消費増税)を定着化させる根拠に悪用される
-
消費税標準税率(現行10%)の更なる引き上げの布石になる *食料品など生活必需品の税率を大幅に低く設定した諸外国では標準税率は20%超と高く設定している例が多々あり、現に後述の開示文書にて財務省が例示
このように、「減税」よりも「増税」の意味合いが強い実態を踏まえると、筆者は「本政策は財務省の主導では?」という疑念を早くから抱いていました。そこで、本政策が注目され始めた今年(2025年)2月の段階で、この疑念を明らかにできる内容を財務省に開示請求。結果、開示された行政文書5件(計72枚)には、本政策が財務省の主導であると断言できるほど決定的証拠は含まれませんでしたが、以下のような実態は見えてきました。
-
立憲民主党と維新の国会議員は明らかに本政策を推進する意図で早くから財務省に様々な働きかけを行い、財務省側も応じていたこと
-
約3ヶ月に及ぶ攻防を経て最終的には行政文書5件の開示に成功したものの、官公庁や自治体への開示請求経験が150件を超える筆者ですら初めて経験する巧妙な手口で財務省は開示を避けようとした(=本政策への関与を隠そうとした)こと
今回のニュースレターでは、これらの実態を自らの開示請求結果に基づいて詳しくお伝えしてきます。
本編の目次
-
開示請求の概要
-
示唆に富む開示文書5件の中身
-
巧妙な手口で開示を避けようと企んだ財務省との攻防
*今回は完全独自のため、続きはサポートメンバー限定で公開します。一定期間経過後も無料読者には公開されません。
*サポートメンバー登録(月額600円~、解約はいつでも可)すると、今後も継続して発信予定の消費税・インボイスを含む全ての記事をいち早く読むことができます。さらに、過去の配信分も含めて有料コンテンツが全て閲覧できます。
*ニュースレターの重点テーマ、特に反響が大きかった過去のコンテンツは「概要」を参照ください
提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績